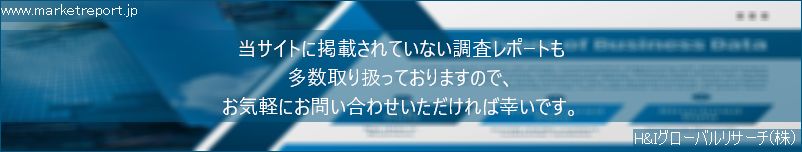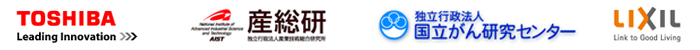1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 グローバル大豆食品市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品タイプ別市場分析
5.5 カテゴリー別市場分析
5.6 流通チャネル別市場分析
5.7 最終用途別市場分析
5.8 地域別市場分析
5.9 市場予測
6 製品タイプ別市場分析
6.1 テクスチャード・ベジタブル・プロテイン(TVP)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 豆乳
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 大豆油
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 豆腐
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 カテゴリー別市場分析
7.1 有機
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 従来型
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 流通チャネル別の市場区分
8.1 スーパーマーケットおよびハイパーマーケット
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 デパート
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 コンビニエンスストア
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 オンライン
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 乳製品代替品
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 肉代替品
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 ベーカリーおよび菓子
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 機能性食品
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 乳児用栄養食品
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 アジア太平洋地域
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 北米
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東およびアフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 ラテンアメリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
14.1 価格指標
14.2 価格構造
14.3 マージン分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 ブルーダイヤモンド・グローワーズ
15.3.2 ディーン・フーズ
15.3.3 アースズ・オウン・フード・カンパニー
15.3.4 イーデン・フーズ
15.3.5 フリーダム・フーズ・グループ
15.3.6 ハーベスト・イノベーションズ
15.3.7 ハウスフーズアメリカホールディング
15.3.8 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド
15.3.9 ミラクル・ソイビーン・フード・インターナショナル社
15.3.10 カーギル
15.3.11 ノルディック・ソヤ社
15.3.12 ビクトリア・グループ
15.3.13 ヘイン・セレスティアル
15.3.14 アディソイ・フーズ&ビバレッジズ社
表2:グローバル:大豆食品市場予測:製品タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:大豆食品市場予測:カテゴリー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:大豆食品市場予測:流通チャネル別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:大豆食品市場予測:最終用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:大豆食品市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:大豆食品市場の構造
表8:グローバル:大豆食品市場:主要企業
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Soy Food Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Category
5.6 Market Breakup by Distribution Channel
5.7 Market Breakup by End-Use
5.8 Market Breakup by Region
5.9 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Textured Vegetable Protein (TVP)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Soy Milk
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Soy Oil
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Tofu
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Category
7.1 Organic
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Conventional
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Distribution Channel
8.1 Supermarkets and Hypermarkets
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Departmental Stores
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Convenience Stores
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Online
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End-Use
9.1 Dairy Alternatives
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Meat Alternatives
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Bakery and Confectionary
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Functional Foods
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Infant Nutrition
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Others
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 Asia Pacific
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 North America
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Middle East and Africa
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Latin America
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
14.1 Price Indicators
14.2 Price Structure
14.3 Margin Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Blue Diamond Growers
15.3.2 Dean Foods
15.3.3 Earth's Own Food Company
15.3.4 Eden Foods
15.3.5 Freedom Foods Group
15.3.6 Harvest Innovations
15.3.7 House Foods America Holding
15.3.8 Archer Daniels Midland
15.3.9 Miracle Soybean Food International Corp
15.3.10 Cargill
15.3.11 Nordic Soya Oy
15.3.12 Victoria Group
15.3.13 Hain Celestial
15.3.14 Adisoy Foods & Beverages Pvt. Ltd.
| ※参考情報 大豆食品は、大豆を主成分とする食品の総称であり、世界中で広く Consume されている栄養価の高い食品です。大豆は、東アジアの伝統的な食文化に深く根ざした食材であり、肉類や乳製品の代替としても注目されています。大豆の栄養価は非常に高く、良質な植物性タンパク質を豊富に含んでいるため、ベジタリアンやヴィーガンの食生活において重要な役割を果たします。 大豆食品には、豆腐、納豆、味噌、醤油、テンペ、エダマメなど多岐にわたる種類があります。豆腐は、大豆を水に浸してすり潰し、煮てから凝固剤で固めたものです。さまざまな料理に使われるだけでなく、食べやすく消化しやすいことから、多くの人々に親しまれています。納豆は、大豆を発酵させたもので、日本で非常に人気のある食品です。納豆に含まれるナットウキナーゼは、血栓予防の効果があるとされており、健康食品としての側面も持ち合わせています。 味噌は、大豆を主成分とし、麹と塩で発酵させた調味料で、日本料理に欠かせない存在です。また、醤油は、大豆と小麦から作られる発酵調味料で、さまざまな料理に風味を加える役割を果たします。テンペはインドネシアの伝統的な大豆食品で、大豆を発酵させて作られ、独特の風味と食感があります。エダマメは、若い大豆を茹でて食べるもので、栄養が豊富でスナック感覚で楽しめます。 大豆食品の大きな利点の一つは、植物性タンパク質を豊富に含むことです。動物性タンパク質と比較しても、アミノ酸バランスが良く、体に必要な栄養素を効率的に摂取することができます。さらに、大豆には食物繊維が豊富に含まれており、腸内環境の改善や便秘の解消にも寄与します。加えて、大豆に含まれるイソフラボンやサポニンは、抗酸化作用やホルモンバランスの調整に役立つとされています。 最近では、代替肉としての大豆食品の需要が増しており、特にヴィーガンやベジタリアンの人々に支持されています。大豆を原料とした「肉」製品は、見た目や食感、味わいにおいても肉に似せることができるため、食事制限をしている人々にも取り入れやすい食品として注目されています。さらに、環境への負荷が少ないことから、持続可能な食生活を志向する動きとも関連しています。 また、大豆食品は、さまざまな料理に利用できる versatility を持っています。サラダ、スープ、煮物、揚げ物、焼き物など、多様な調理法に対応できるため、食卓に彩りを加えることができます。特に大豆を使用した加工食品は、手軽に取り入れることができ、忙しい現代人にとって非常に便利な食品です。 大豆食品にはいくつかの注意点もあります。例えば、大豆に含まれるフィチン酸は、ミネラルの吸収を妨げる可能性があるため、過剰に摂取することは避けた方が良いでしょう。また、メッセージが誤解を招くこともあるため、特定の健康効果を謳う際には、科学的根拠を確認することが重要です。個々の体質によって消化が難しい場合もあるため、初めて大豆食品を取り入れる場合は、少量から始めて様子を見ることをお勧めします。 以上のように、大豆食品はその栄養価の高さや調理の多様性から、食生活において非常に重要な位置を占めています。日本だけでなく、世界中で注目されている食品であり、これからもその需要は増加していくと考えられます。健康志向の高まりや環境への配慮から、大豆食品を取り入れることは、より良い食生活を実現するための一つの手段として、非常に有意義であると言えるでしょう。 |