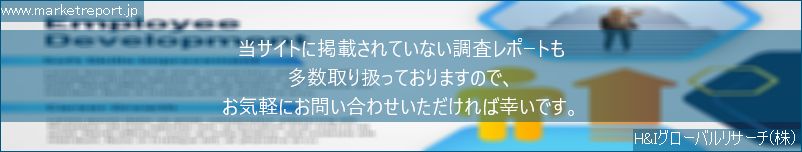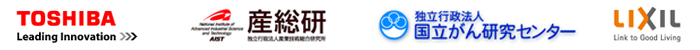1 市場概要
1.1 データセンター用液浸冷却液の定義
1.2 グローバルデータセンター用液浸冷却液の市場規模と予測
1.2.1 売上別のグローバルデータセンター用液浸冷却液の市場規模(2019-2030)
1.2.2 販売量別のグローバルデータセンター用液浸冷却液の市場規模(2019-2030)
1.2.3 グローバルデータセンター用液浸冷却液の平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.3 中国データセンター用液浸冷却液の市場規模・予測
1.3.1 売上別の中国データセンター用液浸冷却液市場規模(2019-2030)
1.3.2 販売量別の中国データセンター用液浸冷却液市場規模(2019-2030)
1.3.3 中国データセンター用液浸冷却液の平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.4 世界における中国データセンター用液浸冷却液の市場シェア
1.4.1 世界における売上別の中国データセンター用液浸冷却液市場シェア(2019~2030)
1.4.2 世界市場における販売量別の中国データセンター用液浸冷却液市場シェア(2019~2030)
1.4.3 データセンター用液浸冷却液の市場規模、中国VS世界(2019-2030)
1.5 データセンター用液浸冷却液市場ダイナミックス
1.5.1 データセンター用液浸冷却液の市場ドライバ
1.5.2 データセンター用液浸冷却液市場の制約
1.5.3 データセンター用液浸冷却液業界動向
1.5.4 データセンター用液浸冷却液産業政策
2 世界主要会社市場シェアとランキング
2.1 会社別の世界データセンター用液浸冷却液売上の市場シェア(2019~2024)
2.2 会社別の世界データセンター用液浸冷却液販売量の市場シェア(2019~2024)
2.3 会社別のデータセンター用液浸冷却液の平均販売価格(ASP)、2019~2024
2.4 グローバルデータセンター用液浸冷却液のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
2.5 グローバルデータセンター用液浸冷却液の市場集中度
2.6 グローバルデータセンター用液浸冷却液の合併と買収、拡張計画
2.7 主要会社のデータセンター用液浸冷却液製品タイプ
2.8 主要会社の本社と生産拠点
2.9 主要会社の生産能力の推移と今後の計画
3 中国主要会社市場シェアとランキング
3.1 会社別の中国データセンター用液浸冷却液売上の市場シェア(2019-2024年)
3.2 データセンター用液浸冷却液の販売量における中国の主要会社市場シェア(2019~2024)
3.3 中国データセンター用液浸冷却液のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
4 世界の生産地域
4.1 グローバルデータセンター用液浸冷却液の生産能力、生産量、稼働率(2019~2030)
4.2 地域別のグローバルデータセンター用液浸冷却液の生産能力
4.3 地域別のグローバルデータセンター用液浸冷却液の生産量と予測、2019年 VS 2023年 VS 2030年
4.4 地域別のグローバルデータセンター用液浸冷却液の生産量(2019~2030)
4.5 地域別のグローバルデータセンター用液浸冷却液の生産量市場シェアと予測(2019-2030)
5 産業チェーン分析
5.1 データセンター用液浸冷却液産業チェーン
5.2 上流産業分析
5.2.1 データセンター用液浸冷却液の主な原材料
5.2.2 主な原材料の主要サプライヤー
5.3 中流産業分析
5.4 下流産業分析
5.5 生産モード
5.6 データセンター用液浸冷却液調達モデル
5.7 データセンター用液浸冷却液業界の販売モデルと販売チャネル
5.7.1 データセンター用液浸冷却液販売モデル
5.7.2 データセンター用液浸冷却液代表的なディストリビューター
6 製品別のデータセンター用液浸冷却液一覧
6.1 データセンター用液浸冷却液分類
6.1.1 HFE
6.1.2 Fluoroketone
6.1.3 PFPE
6.1.4 PFAE
6.1.5 Other
6.2 製品別のグローバルデータセンター用液浸冷却液の売上とCAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
6.3 製品別のグローバルデータセンター用液浸冷却液の売上(2019~2030)
6.4 製品別のグローバルデータセンター用液浸冷却液の販売量(2019~2030)
6.5 製品別のグローバルデータセンター用液浸冷却液の平均販売価格(ASP)(2019~2030)
7 アプリケーション別のデータセンター用液浸冷却液一覧
7.1 データセンター用液浸冷却液アプリケーション
7.1.1 Single-phase Immersion Cooling
7.1.2 Two-phase Immersion Cooling
7.2 アプリケーション別のグローバルデータセンター用液浸冷却液の売上とCAGR、2019 VS 2023 VS 2030
7.3 アプリケーション別のグローバルデータセンター用液浸冷却液の売上(2019~2030)
7.4 アプリケーション別のグローバルデータセンター用液浸冷却液販売量(2019~2030)
7.5 アプリケーション別のグローバルデータセンター用液浸冷却液価格(2019~2030)
8 地域別のデータセンター用液浸冷却液市場規模一覧
8.1 地域別のグローバルデータセンター用液浸冷却液の売上、2019 VS 2023 VS 2030
8.2 地域別のグローバルデータセンター用液浸冷却液の売上(2019~2030)
8.3 地域別のグローバルデータセンター用液浸冷却液の販売量(2019~2030)
8.4 北米
8.4.1 北米データセンター用液浸冷却液の市場規模・予測(2019~2030)
8.4.2 国別の北米データセンター用液浸冷却液市場規模シェア
8.5 ヨーロッパ
8.5.1 ヨーロッパデータセンター用液浸冷却液市場規模・予測(2019~2030)
8.5.2 国別のヨーロッパデータセンター用液浸冷却液市場規模シェア
8.6 アジア太平洋地域
8.6.1 アジア太平洋地域データセンター用液浸冷却液市場規模・予測(2019~2030)
8.6.2 国・地域別のアジア太平洋地域データセンター用液浸冷却液市場規模シェア
8.7 南米
8.7.1 南米データセンター用液浸冷却液の市場規模・予測(2019~2030)
8.7.2 国別の南米データセンター用液浸冷却液市場規模シェア
8.8 中東・アフリカ
9 国別のデータセンター用液浸冷却液市場規模一覧
9.1 国別のグローバルデータセンター用液浸冷却液の市場規模&CAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
9.2 国別のグローバルデータセンター用液浸冷却液の売上(2019~2030)
9.3 国別のグローバルデータセンター用液浸冷却液の販売量(2019~2030)
9.4 米国
9.4.1 米国データセンター用液浸冷却液市場規模(2019~2030)
9.4.2 製品別の米国販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.4.3 “アプリケーション別の米国販売量市場のシェア、2023年 VS 2030年
9.5 ヨーロッパ
9.5.1 ヨーロッパデータセンター用液浸冷却液市場規模(2019~2030)
9.5.2 製品別のヨーロッパデータセンター用液浸冷却液販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.5.3 アプリケーション別のヨーロッパデータセンター用液浸冷却液販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6 中国
9.6.1 中国データセンター用液浸冷却液市場規模(2019~2030)
9.6.2 製品別の中国データセンター用液浸冷却液販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6.3 アプリケーション別の中国データセンター用液浸冷却液販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7 日本
9.7.1 日本データセンター用液浸冷却液市場規模(2019~2030)
9.7.2 製品別の日本データセンター用液浸冷却液販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7.3 アプリケーション別の日本データセンター用液浸冷却液販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8 韓国
9.8.1 韓国データセンター用液浸冷却液市場規模(2019~2030)
9.8.2 製品別の韓国データセンター用液浸冷却液販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8.3 アプリケーション別の韓国データセンター用液浸冷却液販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9 東南アジア
9.9.1 東南アジアデータセンター用液浸冷却液市場規模(2019~2030)
9.9.2 製品別の東南アジアデータセンター用液浸冷却液販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9.3 アプリケーション別の東南アジアデータセンター用液浸冷却液販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.10 インド
9.10.1 インドデータセンター用液浸冷却液市場規模(2019~2030)
9.10.2 製品別のインドデータセンター用液浸冷却液販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.10.3 アプリケーション別のインドデータセンター用液浸冷却液販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.11 中東・アフリカ
9.11.1 中東・アフリカデータセンター用液浸冷却液市場規模(2019~2030)
9.11.2 製品別の中東・アフリカデータセンター用液浸冷却液販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.11.3 アプリケーション別の中東・アフリカデータセンター用液浸冷却液販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
10 会社概要
10.1 3M
10.1.1 3M 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.1.2 3M データセンター用液浸冷却液製品モデル、仕様、アプリケーション
10.1.3 3M データセンター用液浸冷却液販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.1.4 3M 会社紹介と事業概要
10.1.5 3M 最近の開発状況
10.2 Chemours
10.2.1 Chemours 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.2.2 Chemours データセンター用液浸冷却液製品モデル、仕様、アプリケーション
10.2.3 Chemours データセンター用液浸冷却液販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.2.4 Chemours 会社紹介と事業概要
10.2.5 Chemours 最近の開発状況
10.3 Solvay
10.3.1 Solvay 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.3.2 Solvay データセンター用液浸冷却液製品モデル、仕様、アプリケーション
10.3.3 Solvay データセンター用液浸冷却液販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.3.4 Solvay 会社紹介と事業概要
10.3.5 Solvay 最近の開発状況
10.4 Juhua
10.4.1 Juhua 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.4.2 Juhua データセンター用液浸冷却液製品モデル、仕様、アプリケーション
10.4.3 Juhua データセンター用液浸冷却液販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.4.4 Juhua 会社紹介と事業概要
10.4.5 Juhua 最近の開発状況
10.5 Shell
10.5.1 Shell 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.5.2 Shell データセンター用液浸冷却液製品モデル、仕様、アプリケーション
10.5.3 Shell データセンター用液浸冷却液販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.5.4 Shell 会社紹介と事業概要
10.5.5 Shell 最近の開発状況
11 結論
12 付録
12.1 研究方法論
12.2 データソース
12.2.1 二次資料
12.2.2 一次資料
12.3 データ クロスバリデーション
12.4 免責事項
| ※参考情報 データセンター用液浸冷却液は、IT機器を冷却するために液体に浸す方式の冷却技術を使用するための特別な流体を指します。データセンターでは、サーバーやストレージデバイスなどの電子機器が集中的に運用されており、これらの機器から発生する熱を効率的に管理することが重要です。液浸冷却は、この熱管理のための革新的なアプローチの一つであり、従来の空冷方式と比べて多くの利点を持っています。 液浸冷却の基本的な概念は、電子機器を絶縁性のある冷却液に浸すことで、直接的に熱を取り除くというものです。この手法は、冷却液自体が熱を吸収し、効率的に熱を散逸させる特性を持つため、機器の温度を安定させることができます。また、熱交換の効率が高く、冷却能力に優れているため、高密度なサーバー配置が可能となります。 液浸冷却液の特徴としては、まず第一にその絶縁性が挙げられます。液浸冷却に使用される液体は、電子機器との接触があっても短絡や腐食を引き起こさないため、セキュリティが保たれています。さらに、液体が機器の周囲全体を包み込むことで、均一な冷却が実現され、過熱のリスクを低減します。また、液浸冷却ではファンなどの動作部品が不要な場合が多く、騒音が抑えられるという利点もあります。 液浸冷却液の種類は多岐にわたりますが、主に二つのカテゴリに分けられます。第一に、有機冷却液であり、これは石油から派生した液体群に分類されます。このタイプの冷却液は、比較的低コストで入手できるため、多くのデータセンターで利用されています。第二に、無機冷却液があり、こちらは水や冷却剤を使用するケースが一般的ですが、これらは高い絶縁性を持っていません。そのため、無機冷却液を使用する場合は、機器に対して適切な防護策を講じる必要があります。 液浸冷却はさまざまな用途があります。特に、高密度でのコンピューティング環境において、サーバーの冷却が大きな課題となります。このような環境では、液浸冷却を導入することで省スペース化が可能となり、必要な冷却能力を確保しつつ効率的に運用することが実現できます。また、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、ビッグデータ分析、AI演算など、特に熱発生量の多いアプリケーションでも有利です。これらの運用において、液浸冷却は省エネルギーを図る手段としても注目されています。 さらに、液浸冷却は関連技術との連携によって性能を向上させることが可能です。液浸冷却と冷却システムを統合する場合、熱回収システムと組み合わせることで、廃熱を有効活用することができます。例えば、熱を回収し、それを暖房用途に転用することも可能です。このように、循環型経済の観点で持続可能性を高めることも重要なテーマとなります。 データセンターにおいて、液浸冷却技術は今後ますます普及することが予想されます。近年では、ますます多くの企業がこの技術の実用化に取り組んでおり、実際に導入を進める動きが加速しています。これに伴い、液浸冷却液の開発も進展しており、より効率的でコストパフォーマンスに優れた製品が市場に登場しています。 こうした技術革新に伴い、液浸冷却は未来のデータセンターにおける冷却手法としての地位を確保することでしょう。この革新的なアプローチは、温暖化の進行やエネルギー消費の削減を目指した持続可能な社会に資する重要な手段となることが期待されています。データセンター向けの液浸冷却液の概念は、今後も技術の進歩とともに進化し、エネルギー効率の向上と運用コストの削減を同時に実現する革新を提供することに寄与するでしょう。 |